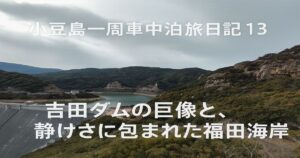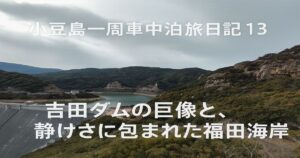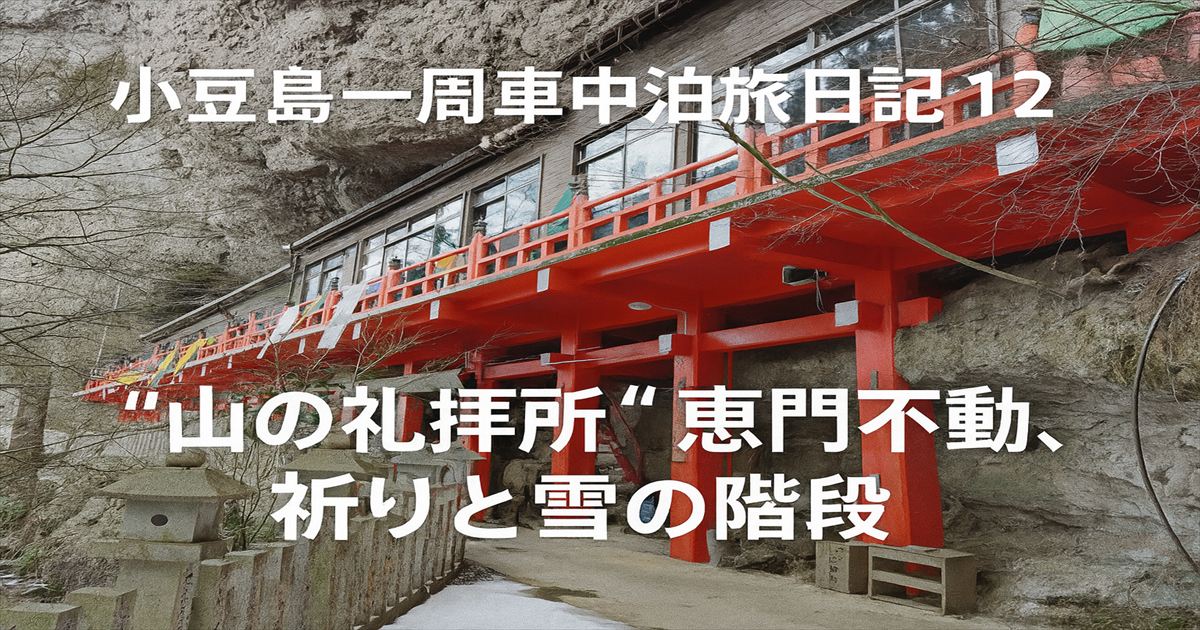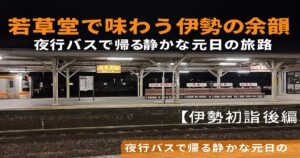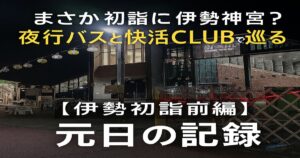島の北側を巡る三日目の道中。
この日、目指したのは「山の礼拝所」と呼ばれる恵門不動(えもんふどう)。
「海の礼拝所=江洞窟」と対になるように、買ったガイドブックに紹介されていた場所。
静かな空気をまとったあの一帯の記憶は、今も印象深く残っています。
↓前回の記事はこちら

恵門不動への道は、愛車と共に挑む“山越え”
道の駅を出発し、目的地へと車を走らせる。
重岩の坂道もなかなかのものだったけれど、恵門不動はさらに上をいく山道。
急こう配に加え、舗装の荒い場所も多く、運転中は気が抜けない。
それでも、こうして目的地へ連れてきてくれる愛車に感謝しながら、静かにハンドルを握る。

ようやく辿り着いたのは、トイレ付きの広い駐車場。
これほどの規模ということは、観光客の多い時期にはそれなりに人が訪れるのかもしれない。
ただしこの日は平日ということもあるからか自分1人。
加えて、トイレは「故障中」で使用不可。
今のところ修繕の予定もなさそうな雰囲気だった。
🌀 故障中のトイレを目にして感じたのは、
この場所が「誰かの日常的な管理下」には置かれていないこと。
それでも、山の奥にこうして祈りの場が残っていることに、不思議な敬意を覚える。

ちなみにトイレは上にあります。
階段を歩いて、観音の道へ
ここから先も車で進める道はあるけれど、急ぐ旅でもない。
せっかくだからと、自分の足で階段を登ることにした。
まず現れたのは、如意輪観音菩薩のいらっしゃるお堂。
中はやはり手入れされている感じではないけれど、ここまで残っているだけでもありがたい。
さらに登ると、聖観世音菩薩がまた右手にいらっしゃった。
それぞれ手を合わせてから先に進ませてもらう。
封鎖された鐘楼の道、荒れた階段を越えて
階段を進むと鐘楼への道にはロープが張られていた。
おそらく、台風などで飛ばされた瓦などの落下物を警戒しての措置だろう。

風の通り道である山の中。
自然の力は時に厳しく、そして容赦がない。
一瞬、引き返すかと悩んだが、ここまで来たのだからと慎重に進む。
この鐘楼も修繕される時は来るのだろうか…と思いつつ通過する。
鐘楼を抜けた階段には道を塞ぐような草木。
普段から誰も踏み入れていないことがわかる。
冬の枯れ草だからまだ通ることはできたが、夏だと更に道が塞がれていそうだった。
足跡のない雪と、祈りの静けさ
いよいよ、恵門不動が見えてくる位置にたどり着いた。
階段に薄く積もった雪が、「今日はまだ誰も観光客がここまで来ていない」ことを物語っていた。

階段の周囲も見て、ゆっくりと登っていく。
階段を登りきったところに残る足跡は、恐らく住職がトイレに行くために歩いたものだろう。
それ以外には、人の気配はない。
それにしても、こんな険しい場所に祈りの場を築いた人間の意思には驚かされる。
どれだけの思いを込めて、ここに不動明王を祀ったのだろうか。
人の信仰というものの力強さに、ただただ感服する。
通路の奥には、登山者向けと思しき鎖場もあった。
選ばれし者だけが通る「もうひとつの道」といった風情。

恵門不動の内部と、住職のあたたかさ
中に入ると、岩肌の奥まった部分は光が届かず、ひんやりとしていた。
そこへ住職の方が現れ、灯りとろうそくを灯してくださる。

静寂の中での参拝。
この空間は、単なる観光地ではなく、まぎれもなく“祈りの場”だった。
じっくりと空間を味わい、参拝を終えて出ようとしたそのとき――
住職が木片のお守りを手渡してくださった。
これ(お守り)は来た人に渡してる。気をつけて帰ってね
思いがけない優しさに、心があたたかくなる。
階段で来たことを伝えると、
「もっと近くまで車で来れたよ~」と、軽やかに教えてくださった。
厳かな場の中にも、こうしたやわらかな会話があると救われる。
🌱 とても親しみやすい、あたたかな住職だった。
一人旅だからこそ、こういう時間が好きだと思う
人のあふれる観光地でなくても、
こうして静かに迎えてくれる場所に触れると、来て良かったと素直に思う。
情報の時代にあって、“ここまで来ないと出会えない静けさ”が、確かに存在する。
旅はまだ続くけれど、今日のこの瞬間を、しっかりと胸に刻んでおこう。
次回につづく──島の石と海が語る、静かな風景へ
静謐な祈りの場・恵門不動をあとにして、
小豆島旅は石の記憶と海のきらめきに包まれる道へ。
次回は、「吉田ダム」からスタート。
球体のオブジェと巨大な像、そこにある静けさ。
観光パンフレットには載らない、けれど確かに心に残る場所たち。
誰もいない展望台、海を望むダム、そして福田海岸。
島の“静”の一面が、じわりと染み込んでくる時間を記録します。🌊