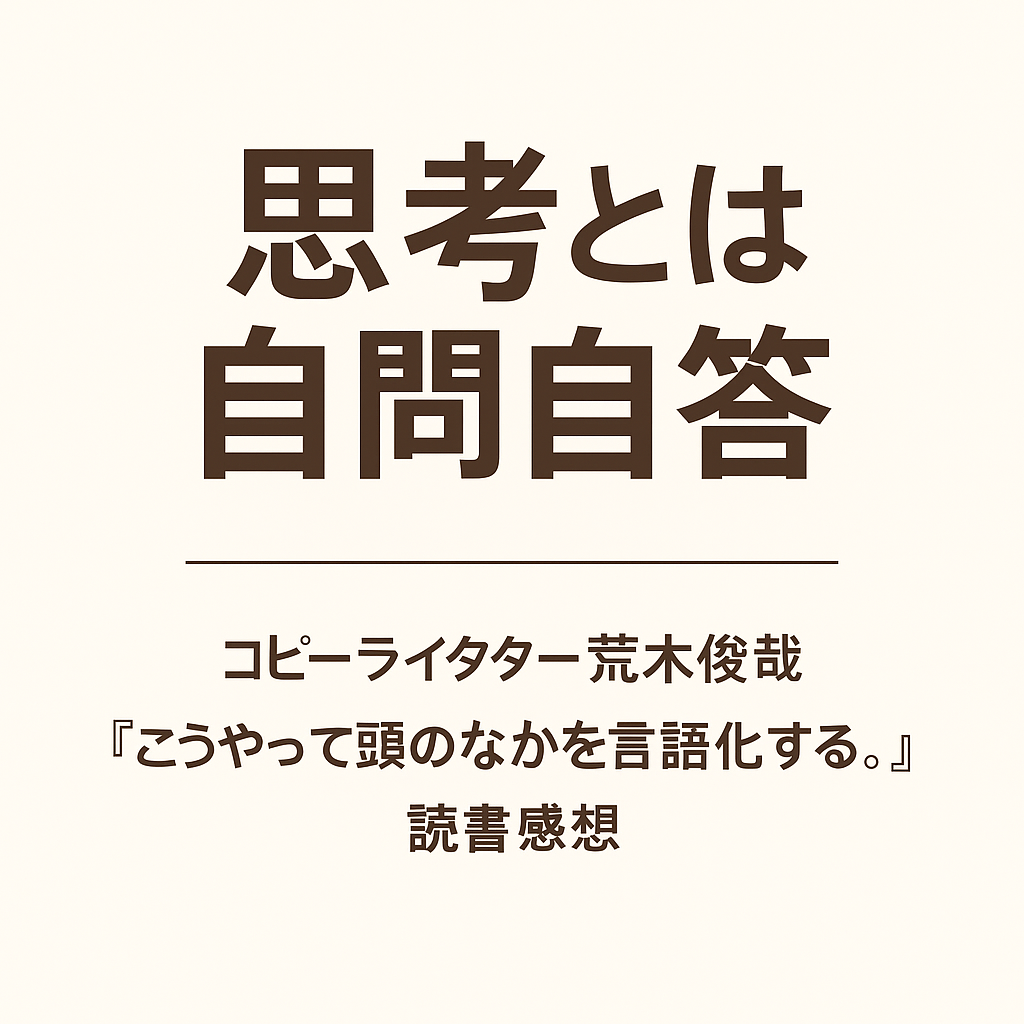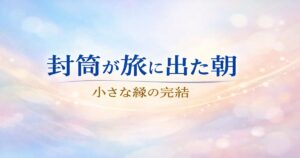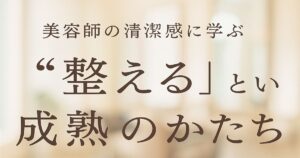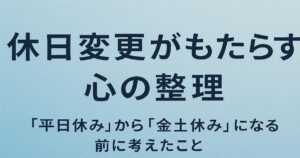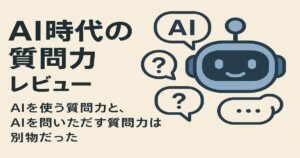コピーライター荒木俊哉さんの著書
『こうやって頭のなかを言語化する。』を読み終えました。
言語化を習慣にするノート術が記されていますが
ここではノート術に関する詳細ではなく
自分の記録として、特に印象に残った部分をまとめておきたいと思います。
コピーライターの仕事は「閃き」ではなかった
コピーライターというと、その場でパッと名フレーズを生み出す閃きの人というイメージを持っていました。
しかし本書を通して、それは誤解だったと知りました。
芸人が大喜利で即興の答えを出すのとは違い、コピーライターは 思いつきでコピーを作っているのではない のです。
荒木さんはまず、クライアントや生活者の話を徹底的に聞き出します。
意識しているのは、相手の言葉を引き出していくこととのこと。
言語化につながる聞き方のコツは「相手の言葉に『関わる』姿勢で話を聞く」
更に相手の辞書を作るイメージを意識していくという。
そして聞き終えると、コピーを考えるターンになる
そこでは自分に問いかけ、自分自身の声を聞いていく。
この一連の行為こそがコピーライターの思考のプロセスでした。
何かコピー考えてよwって言われて、突発的に出せる工程じゃないですね。
「思考とは自問自答」という気づき
本書の中で、もっとも心に残った言葉があります。
- 思考量 = 自問自答の量
- 思考の質 = 自問自答の質
この一文を読んだ時、強く腑に落ちました。
私は普段こうしてブログを書いていますが、これもまた自問自答に近い行為なのだと思います。
昨今では考える時間、思考する時間がなくなってきています。
スマホがあればSNSに動画視聴に漫画にゲームなんでもござれ。
自分にとってはブログをあーでもないこーでもないと
考えながら書いているのは一種の自問自答かもしれません。
その過程で考えが整理され、次第に自分の軸が見えてくる感覚があります。
AI時代の読書と自問自答
最近では、読書感想文をAIに書かせる学生が増えているそうです。
確かに効率的で、タイパ的には合理的かもしれません。
しかし、私にとって本を読むことは「思考の触媒」です。
AIに要約してもらえば要点は理解できるでしょうが、自分がどこに心を動かされたかまでは代わりに拾ってはくれません。
だからこそ、本は自分の思考を深める相手であり
読書とは自分の思考を深めるためのエッセンスです。
ブログまたは読書感想はその思考を整理する場所であると感じています。
AIに要約させることは確かに要点を掴むには最適ですが
個人的にはエッセンスを捨てているように思います。
例えば荒木さんの本書をAIに読ませれば、言語化ノート術のやり方を説明はしてくれるでしょう。
けれど、私にとって一番印象に残った「思考とは自問自答」という気づきは
言語化ノート術に関係はないと、スルーされてしまうはずです。
答えを得たいだけならAIに頼ればいいですが
思考を深めたいなら自分で読むしかない。
だから読書感想文という宿題の答えを得たかった学生は目的を果たしたなら
それを間違っていると自分の考えを押し付ける気はありません。
ただ、思考を深めるのが好きな身としては勿体ないなと感じる次第です。
言語化は「生きる力」そのもの
本書の中で、もう一つ印象に残った言葉を記しておきます。
インフルエンサーは答えを持っていない。人の数だけ答えがある。
自分の「軸」をしっかり言語化することが、自分にとっての答えを見つける近道。
言語化は生きる力そのもの。どんな資格よりもまず「自分」を学べ。
この言葉に強く共感しました。
私自身、かつて前の部署を辞める時に胸の内を日記に書き殴った経験があります。
その過程で、なぜ辞めたいと思ったのか、何が嫌だったのかを言葉にできたことで、やりたくない仕事の方向性が見えてきました。
何が好きかも大事ですが、何が嫌なのかを知ることでも
自分軸が見えてきます。
つまり言語化は、自分を理解するための学びそのものなのだと思います。
これからもブログは「思考の場」として
知りたいことはSNSで知ることもできますし
検索すればAIの回答が検索結果にも表示される時代になり、
ブログは「時代遅れ」と見られるのかもしれません。
それでも私は、これからもブログを書き続けると思います。
なぜなら、ブログを書くことが自分にとっての自問自答だからです。
そしてその積み重ねが、自分の言語化力になると信じているからです。
言語化ノート術も習慣にできたらいいなと思っています。
なので実践しつつ、この本はその過程で読み返していきたいですね。