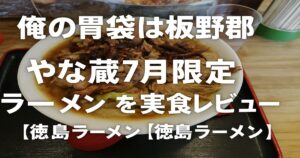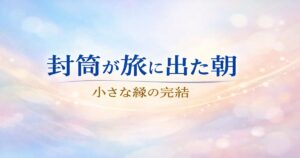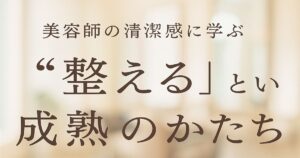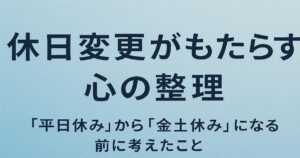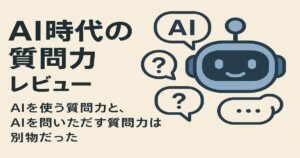最近、ドラゴン桜やインベスターZでおなじみの三田紀房先生のセミナー音源を、車の中で久しぶりに聞き返しました。
この音源は「平成進化論」というメルマガが主催したもので、検索してもほとんど情報が出てこないほどのプライベート性の高いセミナーです。
改めて聞き返して思ったのは、やはり人の話には学びと気付きが詰まっているということ。
しかも音源のいいところは、聞くタイミングによって響くポイントが変わるところです。
以前は聞き流していた部分が、今の自分にはすごく刺さったりもします。
今回は、そのセミナーの中でも特に印象に残ったポイントを自分の記録として整理しました。
漫画家の職場改革から学ぶ「マネジメントの極意」
三田先生はアシスタントを抱える個人事業主のような立場。
当然、アシスタントのマネジメントが必要で、退職=離職は大きな痛手となります。
そこで三田先生がまず取り組んだのは、
📌 「徹夜をやめる」こと。
先輩漫画家のスタイルに倣い、昼過ぎに集まって夜中まで作業するのが業界の常識でしたが、あえて朝から夜のはじめ頃までの9時間労働を提案しました。
実際にやってみると、
✅ 集中力が上がる
✅ 3日休み・4日稼働の働き方が定着(最終日のみ原稿完成するまでやる)
お菓子を常備してだらだら作業する習慣も見直し、職場の雰囲気そのものを健全化させたのです。
業界の常識=社会の非常識
この発想を疑い、働きやすさを優先したのがポイントです。
人間関係の95%は「生活スタイル」で解決できる
就業時間を変えることで職場の改善はされたとして
次に問題となるのが人間関係です。
どんな仕事場も離職の理由には人間関係が大きく関わってきます。
特に漫画家のアシスタント志望の人は、部活動をやったことがないことが多いとのこと。
美術部とかはあるかもしれませんが、団体行動の運動部出身はそういない感じのようです。
辞めたいというアシスタントに話を聞くと、きっかけは本当に些細なことが多かったという。
- 自分はマグカップを洗って帰るのに、相手はそのまま放置
- スリッパを脱ぎっぱなしで帰る
- その小さな不公平感が、やがて相手の作業音すら不快になる
こうした不満を解決するために、三田先生は就業規則を作成しました。
📝 例:就業規則の内容(一部)
- スリッパは揃えましょう
- 自分で使ったマグカップは洗いましょう
- 掃除をして帰りましょう
- お金や物の貸し借りは禁止
行動を統一することで、自分はやっているのに、あいつはやらないといった
不公平感がなくなり、人間関係が改善しました。
嫌いって言っていた子が、相手と仲良く雑談して帰っていくように変化したとか。
同じ行動を取ることで集団意識が強化され親近感が生まれたのかもしれません。
三田先生も相手の人格が嫌いだとか、考え方が気に入らないということはほとんどない
生活スタイルの違いが亀裂を生むキッカケになるとの持論です。
電話対応も「マニュアル化」する
ある日、職場に遅れていった三田先生が、アシスタントから「さっき電話鳴ってました」と報告を受けます。
内容を聞き返して驚いたのは、電話が鳴っても誰も出ていないことでした。
漫画家宛ての電話は個人宛のようなもので、アシスタントたちは他人宛の電話を
「出ていいのか分からない」という心理でスルーしてしまったのです。
ここで三田先生が取ったのは、
📌 新人を電話係に任命すること。
さらに「次から取ってね」だけで終わらせず、電話対応マニュアルを張り出したのです。
- 「もしもし三田です」から始める
- 出版社からの電話は「いつもお世話になっております」
- 在中なら「ただいま代わります」不在時は「席を外しております」の慣用句まで細かく記載
これにより、新人でも迷わず対応できる環境が整いました。
電話対応は「できて当然」という暗黙の文化がありますが、マニュアル化することでトラブルや不満を未然に防げるのです。
特に昨今のZ世代はSNSコミュニケーションをして育っているので
こうした電話対応ですらマニュアル化されていると助かるでしょうね。
電話なんて誰でもできる、先輩の会話を聞いて学べというよりも
マニュアルの方が言葉遣いでミスなく身につくと思います。
Z世代は電話の取り方すら知らないと嘆いている企業は真似してみてはどうでしょうか。
締切厳守が信頼を生む
三田先生は漫画家の世界では珍しく、締切を必ず守る人です。
業界では「締切は伸ばせる」が暗黙のルールになりがちですが、社会人経験のある三田先生は「期限は守るもの」という意識を徹底。
✅ 週刊2本連載しながらストックも2〜3週分確保
結果、編集部からの信頼は厚く、週間2本やってるのに
◯◯描きませんか?と声がかかるレベルに。
こうした基本的な事が、編集部からの新規案件の依頼や評価アップに直結しているのです。
三田先生の「自由」へのこだわり
三田先生が大切にしている価値観は「自由」。
実家の衣料品店を継いでいた頃は借金返済に追われ、問屋や銀行に支配される日々を送っていました。
人が作ったもの(商品や仕組み)に乗っかるしかない人生には自由がなかった。
その経験から、今の自分が主軸になれる漫画家という道は合っているようです。
大半の漫画家は載せてくださいの立場かもしれませんが
信頼性の高い三田先生は「描いてください」と需要がある存在でいつまでいられるか
自由を確保するために自己PRや信頼の積み重ねを怠らないと語っていました。
三田先生の職場も“完璧”ではなかった
ここまで紹介したマネジメント術は本当に参考になるものばかりですが、
三田先生の職場も決して完璧だったわけではありません。
実は、元アシスタントから残業代の請求があったことが過去にありました。
漫画業界では「変形労働時間制」という特殊な働き方が採用されるケースが多く、
特定日の労働時間が長くても週全体で労働時間が収まっていれば残業代が発生しない制度があります。
しかし、これはしっかりと周知させておかなければ無効となります。
元アシスタントの証言では周知不足の他に…
- 原稿最終日は10時間以上の長時間労働
- 休憩時間も労基法では1時間は必要なはずが小学校の休み時間程度しかない
など、実質的には残業代が発生する状況も多かったようです。
ただ、三田先生の職場はタイムカードを導入していたため、
元アシスタントも過去の残業代を請求がしやすく、
結果的に職場の問題点が明確になりました。
問題提起が改善のきっかけになる
この件も、労働環境をより良くするための一つのステップだったのだと思います。
三田先生も問題提起してくれた事に対して感謝し
未払の残業代を払うことで解決となりました。
聞き返して気づいたことと、自分の職場のこと
この話を聞いて、自分の職場も決して労基法を満たしていない部分があると改めて感じました。
例えば…
- 有給をひと月に2回目取得すると減給になる“トラップ”(ノーペナはひと月に1有給まで)
- そうしたことを行っているので就業規則が明文化して周知されていない
- 本店は有給を取りづらい空気感がある
こうした点は、まさに労働基準法違反になり得るものです。
だからこそ、問題提起をする人がいること自体が重要であり、
それが結果として職場環境の改善に繋がるのだと感じます。
自分の職場で言えば――
💡 有給取得の減給トラップや周知されない就業規則、取得しにくい本店の空気感など、まだまだ改善の余地は多いです。
この2回目以降の有給減給は本店で有給を取得する人がいたことで
ギリギリの人数で回していて、1人いないことで更に負担がかかる
なので有給を取らない人との不公平さをなくす為に減給がという流れらしいですが
これは明確に禁止されている違法行為です。
本来ならば他の人も有給を取得しやすくするべきです。
ただ、自分の勤務する支店は幸い比較的緩やかで
有給も毎月一回は取りやすいのは救いですね。
本店なら本当に用事がないと、メンタルブロックで有給申請しにくいですから。
文句あるなら辞めろよと思うかもしれませんが
意外なことに本店も支店も離職者はほぼいません。
不満があり薄給でありつつも精神的には、比較的はたらきやすい職場である証でもあると思います。
在職中は会社と揉め事を起こすこともありませんしね。
一度だけ別のとこで、こんな生活続けるくらいなら職を失ってでも辞めるって決意したことあるので
そういう時は愚痴る気力もなく、日々ただ頭の中では辞めたいって言葉が渦巻いてましたね。
なんだかんだで文句があったとしても毎日働けるのは今の環境はマシです。
三田先生の生き方と自分の在り方
三田先生は借金返済という逆境の中で自由を求めて行動し続けた人です。
一方で自分は、ぬるま湯の環境に身を置き、ハングリーさを持ちにくい状態にあります。
「人生の主軸を自分で持つ」という三田先生のスタイルには憧れますが、
Being型かつMBTIで冒険家タイプは流されながら生きていくのかもしれません。
その時が来たら、三田先生のように自分の自由を確保できる動き方ができるかどうか?
そんなことを考えさせられた音源でした。